退職代行サービス業者から連絡がきたとき、正しい対応方法は?
最終更新日:2024.11.19
目次
問題の事象
退職代行サービスを名乗る業者から突然電話があり、当社の社員が退職する旨を告げられました。
本人に直接連絡をして意思の確認をしても問題ないでしょうか?
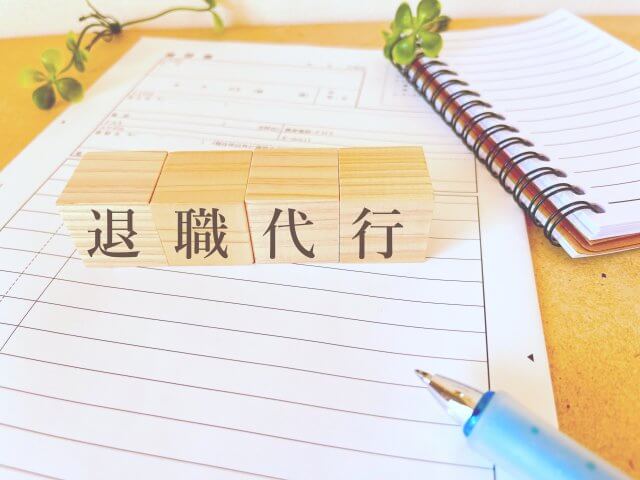
解説(基本的な考え方)
弁護士からの連絡でない場合、本人に意思確認すること自体に違法性はありません。
ただ、ひとまずは本人への直接連絡や意思確認は控えるほうが得策でしょう。
退職代行サービスとは
退職代行サービスとは、退職を希望している従業員に代わり、会社に対して退職の意思表示を行うサービスのことです。
サービスを提供しているのは、弁護士、合同労働組合(ユニオン)、民間の退職代行会社のいずれかです。
サービス提供業者の種類と代行の範囲
弁護士
弁護士は委任契約に基づき、本人の代理として退職代行業務を行うことができます。
代理人として
・退職日、有休消化などの交渉を行う
・裁判に至った場合に対応する
ところまで委任できます。
合同労働組合(ユニオン)
ユニオンは、労働組合がない企業の労働者が加入できる外部労働組合(外部ユニオン)です。
雇用形態を問わず、正社員であっても非正規社員であっても加入できます。
労働組合は会社に対する団体交渉権が認められているため、弁護士でなくても退職日の調整や未払い賃金の支払い請求などの直接交渉ができます。
民間の退職代行会社
退職条件の交渉などを代行するには弁護士資格が必要です。
そのため民間企業が退職代行事業を行っている場合、提供できるサービスは「本人の退職意思を伝えること」のみとされています。
具体的な対応方法
基本的な方針
雇用期間の定めのない従業員は、
2週間前に退職を申し出れば会社の同意なく退職が可能(民法第627条1項)
です。
退職代行サービスを利用の場合、たとえ本人と連絡が取れなくても退職の意思表示は有効で、会社は退職を拒否することはできません。
そのため無理な慰留はせず、円満解決に向けて話し合う姿勢を基本にするのがおすすめです。
退職代行サービスまで利用して退職を希望している社員ですから、仮に翻意したとしても、その後高いモチベーションで業務にあたってもらえる可能性は高くはないでしょう。
対応の手順
1.誰についてか、どの種類の退職代行業者なのかを確認する
どの社員の件なのかはもちろんのこと、連絡してきた退職代行サービス業者が、弁護士、労働組合、民間企業のいずれに該当するのかを必ず確認しましょう。
事業者によって対応方法が変わることもあるため、最初に確認しておくことが重要です。
2.社員本人の意思を確認する
次に、本当に社員本人の意思であることを確認しましょう。
委任状の提示が最適ですが、本人からのメールのようなものでもかまいません。
間違いなく社員本人からの依頼に基づくものだということを、慎重に確認しましょう。
3.回答書を作成する
本人の意思を確認できた場合は、回答書を作成しましょう。
退職代行サービスを利用されたような場合は労働問題に発展する可能性を考慮しておく必要もあり、会社の対応をきちんと証拠に残しておく必要があります。
回答書には
- 退職を認めること
- 退職日についての調整
- 退職日までに行うべき業務(引き継ぎの指示など)
- 会社側の今後の連絡窓口
などを記載し、代行サービス業者宛にできるだけ早く送付しましょう。
本人への直接連絡について
弁護士が退職代行サービスを提供している場合、その弁護士は「法的代理人」としての権限を持っています。
その場合には本人への連絡は控え、その弁護士を通じて社員と連絡を取ることが適切です。
そうでない場合には、社員に直接連絡することは違法ではありません。
ただ、たとえ本人と連絡をしても退職を拒否できるわけでもなく、逆に労働問題への発展リスクに注意が必要となります。
本人確認ができたのであれば、できるだけ代行サービス業者を通して手続きを進めるほうが、円満にすすむ可能性が高いでしょう。
まとめ
退職代行サービス業者から連絡があったときには無理な慰留をせず、円満解決に向けて話し合う姿勢を基本にするのがよいでしょう。
また、回答書のひな型や具体的な対応方法について、事前にしっかりと準備をしておくと安心です。

